(2024.7.23 言論NPO)
言論NPOは、2024年9月3、4日開催の「アジア平和会議」を前に、「2024年の北東アジアの安全保障リスク」について、有識者を対象にアンケート調査を実施し、その上位10位を公表した。この調査は、言論NPOの活動に参加する有識者1000氏を対象に実施し、388氏から回答を得た。
言論NPOは、2024年9月3、4日開催の「アジア平和会議」を前に、「2024年の北東アジアの安全保障リスク」について、有識者を対象にアンケート調査を実施し、その上位10位を公表した。この調査は、言論NPOの活動に参加する有識者1000氏を対象に実施し、388氏から回答を得た。
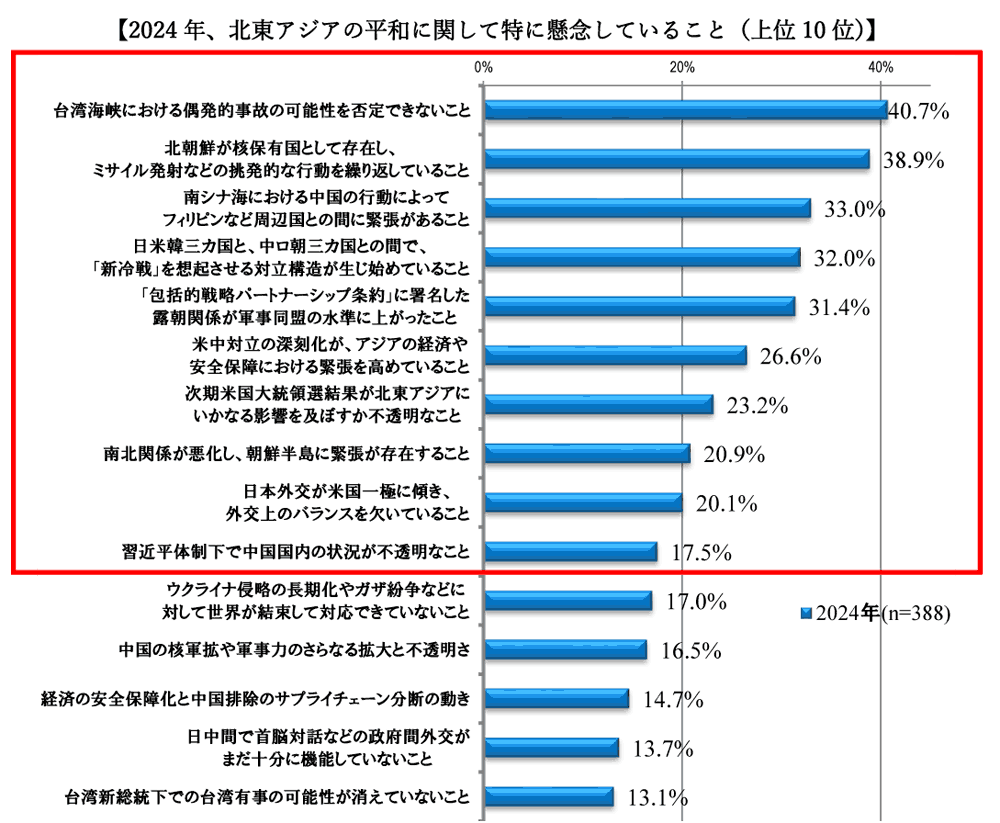

(2024.7.5 La Croix Malo Tresca) ロシア正教のモスクワ聖三位一体教会の主任を務めていたアレクセイ・ウミンスキー大司祭は「ウクライナとの戦いにおける聖なるロシアの勝利」の祈りをミサ中に唱えることを拒否したため、今年1月にモスクワ総主教区での司祭職を解任され、フランスに亡命した。
現在は、パリのノートルダム・デュ・シーニュ・ロシア正教会で奉仕しているウミンスキー大司祭がLa Croixの独占会見に応じ、亡命生活、そしてクレムリン反対派への支援などについて語った。
一問一答は以下の通り。
問: あなたは、ロシアのウクライナ軍事侵攻に公然と反対した数少ないロシア人司祭の一人です。そして、モスクワ総主教区は1月5日にあなたを職務から解任しました。これはどのように起こったのですか、そしてあなたはどう反応しましたか?
答 :私はモスクワ中心部のホフリの聖三位一体教区で30年近く奉仕していました。1月5日、モスクワ総主教庁の特別委員会が、「国内のすべての正教会の司祭が礼拝中に『ウクライナにおける聖なるロシアの勝利』の祈りを唱えているのに、どうしてあなたはそうしないかのか、と私に尋ねました。この委員会は、私が戦争に反対する理由を聞きたくありませんでした。そのわずか数時間後、私は、アンドレイ・トカチェフ大司祭が私の後任として教区長に就任することを知りました。ロシアの民族主義チャンネル『ツァーリ・グラード』の協力者で、ロシアで非常に人気のあるこの司祭は、モスクワ総主教庁とクレムリンを支持していることで知られています…私とはまったく正反対です!
*「モスクワに留まっていたら逮捕される」と警告された
このことは、私と多くの教区民にとって本当にショックでした。私は後任にすべての持ち物を引き渡し、彼にとっての新しい教会、イコン、祭服、聖なる物を紹介しなければなりませんでした…この辛い決断の翌日は、正教会のクリスマスでした。私にとっては喪に服す日のように思われ、教会に行く気はなかった。妻と私はアパートに留まり、友人の司祭が家に来て典礼をし、聖体祭儀をしてくれました。出発前に、この友人は、「あなたに悪い知らせがある… 『モスクワに留まれば逮捕されるだろう』とまじめな人々から知らされた」と忠告してくれました。
問: それであなたは、亡命を急ぎました。 その時、どのような内なるジレンマに直面しましたか?
*高齢の父を置いて、長い亡命の旅に
答: 私はロシアを離れたくありませんでした。特に、今年 89 歳になる父を残しては…。妻から、「でも、お父さまはあなたが海外で一人でいるのを知った方がいいか、それともモスクワにいて刑務所にいるのを知った方がいいのか、どちらです?」と問い詰められ、私は亡命を決めました。電話で脅迫も受けていたので、このままいては危険だと悟りました。それで、わずか 30 分で、小さなバッグに荷物を詰め、ジョージアに向けて出発したのです。
長い旅が始まり、ジョージアから、イタリア、ベルギー、トルコ (ファナールでコンスタンチノープルのバルトロメオス総主教と会いました) を巡り、その後ベルギー、そして最後にフランスへと向かったのです。フランスでは、これまで (編集者注: コンスタンチノープル総主教区のフランス大都市に付属する教区で) 3 か月間奉仕してきました。
問: これらの試練を乗り越えるために、信仰はどのように役立ちましたか?
*「何も恐れるな」と言う詩編の言葉に出会い、”扉”が徐々に開かれた
答: 少し妙かも知れませんが、亡命することで、解放され、落ち着いた気分になりました… 生来、少し衝動的で短気な性格の私は、自分を批判したり、非難したりする人々に対して憎しみや怒りを感じなかったことに、我ながら驚きました。ジョージアに到着し、私は聖職禁止の身にもかかわらず、神、信仰、聖体拝領について語ることができると思っていました。キリスト教徒として、教会での典礼祭儀に出席を続けました。
そして、イタリアのカトリック教会を訪問していた時に、ある”事件”が起こりました。回廊の片側への立ち入りを禁止する標識がありましたが、入り口の扉が半開きだったので、無理やり開けて入ろうとして、指を切りました。その扉の先は、礼拝堂に通じており、「何も恐れるな」という詩篇の一節が目立つように掲げられていました。私はそれを「良い兆し」と感じましたが、実際に、”閉ざされていた扉”が徐々に開かれ、パリのノートルダム・デュ・シーニュ教区での聖職の復活につながりました。私はここで非常に歓迎され、多くの教区民が礼拝に出席してくれています。
問: 今日、ロシア政府の方針を後ろ盾にして言説を過激化し続けているモスクワ総主教区の将来をどう見ていますか?また、ロシアの聖職者の間での(プーチン大統領やそれに組するロシア正教指導部などへの)反対勢力の状況はどうなっていますか?
*プーチンと強く結びついてモスクワ総主教区の将来は不明、でもロシアに残る司祭たちと連絡は欠かさない
答: 率直に言って、モスクワ総主教区はプーチン政権と非常に強く結びついており、これからどうなるのか、分かりません。私は、以前訪問していた政治犯に毎週月曜日に手紙を書き続けています。また、ウクライナ戦争というこの惨事を支持したくないロシアの司祭たちと連絡を取り続けています。彼らは約10人います。私たちはお互いに手紙を書き、私は彼らからニュースを受け取っています。週を追うごとに、状況は悪化しています… 中には、十分な説明もなく、単なる法令によって聖職を禁じられる人もいます。司祭たちへの制裁の手続きは迅速化され、教会の法廷に出廷することさえなくなりました。彼らは控訴する機会を奪われ、何もできない状況に置かれています。
(Photo by Alan Wang / pexels.com)


(左の写真は、最高裁判所玄関)
省庁訪問するときの使用言語の問題があります。通常、アジアの司教団は、どの国から来ても共通語グループは英語に分類されています。したがって、迎える省庁側も、訪問する日本の司教団も、事前に準備するレポートなどはすべて英語で準備します。
とはいえ、日本の司教全員が英語を得意とするわけでもありません。書かれた英語の文章を読むのが得意でも、それと、聞いたり話したりする能力は別です。
日本の司教協議会は、これまでローマに駐在する窓口として、カルメル会の和田神父様にお願いしてきました。和田神父様は、バチカン放送局などに長年勤められた方で、日本政府や皇室などの方々が教皇様を訪問するときにも、教皇庁側の通訳として立ち会うことがあるので、公式の写真などで教皇様の後ろに立っている和田神父様を見かけた方もおられることと思います。(下の写真。真ん中が通訳する和田神父様)
和田神父様はすでに定年を過ぎて延長しておられるので、司教団の窓口としての職務は、今回のアドリミナが最後の仕事になるのではないかと思います。和田神父様の通訳は日本語・イタリア語です。バチカンの省庁の業務上の共通語もイタリア語です。
同時に、日本の司教団17名のうち、イタリア語が分かる方も少なくありませんが、英語と比較すると、英語の方が理解される度合いが高くなります。そこで、基本的に日本の司教団は日本語で話し、省庁側にはイタリア語で話していただいて、すべて和田神父様の通訳を間に挟むことを事前に申し合わせました。
ちなみに教皇様は、英語は、こちらの言うことをほとんど理解しておられますが、話すことがあまり得意ではありません。国際カリタスの業務でお会いするときも、国際カリタス職員のスペイン語話者を通訳として同行させています。
今回は、スケジュールの関係で和田神父様に同行いただけなかった未成年者保護委員会のときだけ、英語でやり取りをすることにして、私が臨時で通訳をしましたが、他は、ほぼイタリア語でのやり取りになりました。
さて、すでに記しましたが、以前のアドリミナでの省庁訪問は、教えられる場でありました。訪問しているこちら側の発言は、ほとんど省庁側からの質問への答えくらいで、あとはひたすら長官などの枢機卿たちの「講話」に耳を傾けたり、省庁の担当者の「教え」を拝聴することで時間が過ぎていました。具体的なことを書くのは憚られますが、省庁訪問の場で、突然に日本の教会のために決められたことを告げられるこ とさえありました。もちろん事前の相談はありません。既述の通り、それも少しずつ変わりつつあります。
とさえありました。もちろん事前の相談はありません。既述の通り、それも少しずつ変わりつつあります。
シノドス的な教会のあり方を目指した改革に加えてもう一つ大きな変化は、以前は省庁の担当者といえば、長官の枢機卿と次官の大司教、そしてその他の役職者もすべて司祭やモンセニョールで、裁判所のような雰囲気のところが大多数でしたが、今回は、様々な省庁で、信徒や特に女性の役職者が明らかに増え、それとともに、穏やかな雰囲気が強まっていたことです。
例えば、総合人間開発省の次官は、シスターAlessandra Smerilli。(左の写真。総合人間開発省で。向かって左から二番目がシスターアレッサンドラ。三番目が長官のチェルニー枢機卿)
奉献使徒的生活省の次官は、シスターSimona Brambilla、いのち・信徒・家庭省の次官補(Under Secretary)は、Linda GhisoniさんとGabriella Gambinoさん。(右の写真はいのち・信徒・家庭省。向かって右端がギソーニさん。左から二番目がガ ンビーノさん。一人おいて長官のファレル枢機卿)
ンビーノさん。一人おいて長官のファレル枢機卿)
シノドス事務局の次官補が、シスターNathalie Becquart。いまシノドスを進めるために重要な役割を果たしているシスターナタリーです。(左下の写真。シノドス事務局で。向かって一番右がシスターナタリー。その隣が長官のグレッグ枢機卿)まだまだ少ないものの主な女性の役職者です。


今の時期は円安ですし、そもそもヨーロッパのホテルはお安くはありませんし、バチカンの近くとなるとなおさらです。そこで、バチカンに近いところにある、かつてはバチカンで働く聖職者の宿舎として建てられた施設に、司教団全員で泊めてもらいました。
サンタンジェロ城(右の写真)の近くにあるこの聖職者の宿舎は、ホテルとまでは言わないものの、現在では空いている部屋を利用して、巡礼者や、私たちのように会議や訪問でバチカンを訪れるグループを、市内のホテルより比較的に安く泊める施設として運営されています。
もともとバチカンで働く聖職者のための宿舎ですから、立派な聖堂がありミサを捧げることができますし、事前にお願いすれば、もちろんそれぞれ有料ですが、朝食だけでなく昼食や夕食を取ることもできます。
以前2015年のアドリミナでもこの施設に泊まったことがありますが、その当時に比べて、インターネットのつながりが格段に良くなっていたことだけは、大きな変化として気がつきましたし、昼食や夕食のお願いも部屋にあるQRコードを読み込んでスマホからできるようになっていました。(左の写真は宿舎の聖堂で朝ミサを司式する中野司教様)
さて、それでは省庁訪問ではどんな話がされたのでしょう。
第一日目、月曜日の最初は、午前9時から、聖職者省へ出かけました。聖職者省の長官は、韓国出身のラザロ・ユ枢機卿様で、日本の司教の多くは、以前からの知り合いです。(右の写真、右がラザロ枢機卿様)
宣教地(日本のような)の司祭養成のための神学校は、いくつかの省庁の管轄下にあります。まず全体の設置や運営の許認可は福音宣教省です。そして、司祭の養成に関しては聖職者省が管轄します。さらに司祭の養成の知的側面に関しては文化教育省になります。全くもって、大変複雑です。
聖職者省では、神学院司教委員会の委員長である大塚司教様が、4月1日に始まった二つの神学院を統合した日本カトリック神学院について、説明をいたしました。その上で、それに伴う様々な規約の改正について、また、現在司教団が整備し、また実際に始めた、司祭の生涯養成のプログラムなどについても説明をしました。
聖職者省からは、特に司祭の生涯養成(神学院での初期養成からはじまり、叙階後の生涯にわたる養成まで)の重要さについて、お話があり、新しく開校した日本カトリック神学校の発展とさらなる召命の発掘についての期待が表明されました。
続いて10時45分から、今度は文化教育省を訪れました。文化教育省の長官は、ホセ・メンドーサ枢機卿様。ポルトガルの出身です。(左の写真は司教たちと握手して回るメンドーサ枢機卿)
聖職者省に続いて、文化教育省でも神学院についての話題になりました。神学院は日本の法律上の学校ではありませんから、学位を取ることはできません。しかし神学院での初期養成の間に、日本で言えば学士にあたる教会上の資格を取得しておかないと、その先にどこかに留学することが難しくなります。また教会内のいくつかの役職のためには、教会上のそういった教育の資格を持っていることが必要になる場合もあります。
そこで、世界中の神学院では、特に自らが大学ではない神学院では、教皇庁立の神学部と提携関係を結び、その神学部から教会上のいわゆる学士などの資格を与えてもらうようにしています。東京カトリック神学院では、これまでローマにあるウルバノ大学と提携していましたが、新しい日本カトリック神学院となることで、この提携関係をあらためる必要があります。そのための具体的な情報交換が行われました。
さらに学校教育委員会の委員長である前田枢機卿様から、日本におけるカトリック学校の実情についての説明があり、司祭や修道者の減少に伴って、学校の現場から司祭修道者が見えなくなっている現実の中で、カトリックとしてのアイデンティティをどのように保っていくのかについて、意見の交換をしました。もちろんこれは長期的課題ですし、日本だけの問題ではなく、すでにかつてキリスト教国であった国でも今やカトリックとしてのアイデンティティをどのように保つかは大きな課題となっているというような内容でした。
また文化教育省からは、大阪万博について日本ではどのような取り組みがなされているのかについての質問がありました。前田枢機卿様から、大阪で取り組んでいる内容について説明をしましたが、すでに文化教育省が承知して進めていることがいくつかあることも確認されました。なお大阪万博への対応についても、バチカンの複数の省庁が関係しており、窓口は一つではないことが、私個人的には複雑な感じがいたしました。
第一日目のお昼12時から、今度は国務省へ向かいました。同じ時間に奉献使徒的生活省も入ってしまっていたため、そちらには山野内司教様やアベイヤ司教様など数名が回りました。(右の写真は、国務省の会議室で、ギャラガー大司教の到着を待つ司教たち)
国務省は、他の省庁と違って、教皇宮殿の中にあるので、そこまでたどり着くのが容易ではありません。スイス衛兵によるいくつかのチェックポイントを通過して、やっと国務省へつながるエレベーターまでたどり着きます。もちろん事前に通知してあるので、スイス衛兵の手元には、誰が何時にどこへ行くのかがすべて記した一覧があり、その一覧を見てのパスです。
パロリン枢機卿は海外出張中で不在のため、国務次官のギャラガー大司教とお会いすることになりました。そのギャラガー大司教も、報道されているとおり、ヴェトナムを公式に訪問されるため、ローマを出発する直前でしたが、じっくりと時間をとってくださいました。ギャラガー大司教は国務省のNO.3で、外務局長となっていますが、いわゆる他の政府で言えば外務大臣です。
ギャラガー大司教との面談では、まず私が司教協議会会長として、能登半島地震への国務長官を通じた教皇様のお見舞いへの御礼を伝え、2019年の教皇訪日の時に様々な尽力してくださった国務省の方々への御礼を伝え、さらに日本における移住者や難民の方々の現状と直面する困難についてお話しし、それに対する日本の教会の対応について説明し、さらに広島教区と長崎教区が中心となって進めている核兵器廃絶への運動について説明をしました。またそれぞれ関係する司教様方から、これらの話題について詳しく説明をいたしました。
ギャラガー大司教からは、特に核兵器禁止条約に国連の場で自ら署名し、バチカンが一番最初に批准した国の一つとなったことについてのお話があり、教皇様が核兵器の保有は倫理に反していると指摘されていることを繰り返され、司教団の核兵器廃絶への取り組みを進めるようにとの励ましがありました。
またギャラガー大司教からは、日本の憲法を巡る現在の政治と社会の情勢について、説明を求められました。
さらに、死刑廃止問題に関連して、特にえん罪によって死刑が執行されることへの懸念についての話となり、司教団からは袴田さんの再審についての状況を説明させていただきました。ギャラガー大司教からは、教皇様がカテキズムを書き直させて死刑廃止を強調されていることに触れて、一朝一夕で実現はできないだろうが、地道な運動が必要だという指摘がありました。
第一日目の午前中は、国務省のこの訪問で、おおよそ午後1時半頃に終了しました。この後午後に二つの訪問がありますが、それはまた後日。(この項、続きます)






 さすがかつては異端審問などをした検邪聖省であったこともあり、歴史のある建物(通称サント・ウフィチオ)は、重々しい雰囲気でした。
さすがかつては異端審問などをした検邪聖省であったこともあり、歴史のある建物(通称サント・ウフィチオ)は、重々しい雰囲気でした。

アドリミナの振り返りの7回目、訪問時の三日目の出来事です。
三日目となる4月10日(水)は、水曜日ですから、本来は一般謁見がある日です。これまた従来ですと、この日の午前中には予定を入れないで、アドリミナ訪問中の司教は一般謁見に参加していました。ここでも教皇様に直接個人的にご挨拶できる機会だからです。しかし今回は、すでに触れたように福音宣教省が予定を組んでくださったため、無慈悲にも、この日も朝8時半から、省庁訪問が組み込まれていました。
実はこの日の一般謁見では、日本聖書協会が、教皇様に聖書を献呈(こちらのリンク)することになっており、当初は私も立ち会う予定でした。献上する聖書は、聖書協会共同訳の大型の講壇用聖書です。日本ではすでにこういった大型本の装丁ができなくなっており、国内で販売しているものについてもオランダの専門家にお願いしていますが、教皇様への献呈聖書はその専門家による特別装丁です。その制作過程はビデオになっています。
私がこれに関わる理由は、日本聖書協会の理事会には長年にわたりカトリック教会から司教が理事として参加させていただいており、現在私が理事として加わり、同時に聖書協会の副理事長を拝命しています。そこで今回のアドリミナに合わせて、日本聖書協会では総主事の具志堅師がローマに渡り、一般謁見の際に私と一緒に教皇様にこの聖書を献呈しようと計画しておりました。
ところが司教たちはその日の朝から他の省庁訪問が入ってしまい、私も一般謁見に同行できなくなったため、急遽、聖書協会の評議員でもある司教協議会の川口事務局長に同行していただくことにして、教皇庁の担当部署にお願いの手紙を出しました。その結果、一般謁見の際に一番前の列に座って、教皇様と数分面談することを許す旨を記した入場券が届き、無事に聖書を献呈することができました。
ケースに入った聖書をお渡しするだけのつもりでしたが、教皇様が開いて手渡すように求められ、さらにじっくりと中まで目を通されたとのことです。後で触れますが、この週の金曜日に教皇様とお会いした際に、この聖書について尋ねたところ、聖書の翻訳は大切な仕事だから力を入れるようにとの言葉をいただきました。(左の写真は聖書協会プレスリリースから)
さて、この水曜日の省庁訪問は、朝8時半からの典礼秘跡省で始まりました。宿舎から、サンピエトロ広場の左手にある典礼秘跡省まで歩いて行く朝の道には、一般謁見に入るための人で、長大な列ができていました。(写真右は典礼秘跡省の入り口)
典礼秘跡省は、長官がアーサー・ローチェ枢機卿。前回2015年の時には、同省の次官だった方です。
典礼秘跡省では、典礼委員長の白浜司教様が、日本での典礼書の翻訳について、同省の迅速な対応への感謝とともに、進捗状況を報告し、新しく出版された日本語のミサ典書をローチェ枢機卿様に献呈しました。(下の写真)
その後意見交換となりました。どれもお互いの考えを述べるのみで、この場で結論の出るような内容ではありませんが、例えば以下のような話題でした。
デジタルでの典礼書や時課の典礼(教会の祈り)の出版について、デジタルが良いのか印刷物が良いのかについての互いの考え。世界の多くの教区で司祭不在の教会が増える中で、集会祭儀と聖体拝領の関係についてどう考えるか。第二バチカン公会議が望んだ典礼刷新を、地域教会で具体的にどう実現していくのか。
またこの中で、司教団が望んでいる「日本205福者殉教者」の名称を、殉教者の中に含まれている日本人で最初の司祭であるセバスチャン木村を筆頭にして、「セバスチャン木村と同志殉教者」に変更することに関して、意見を交換した結果、典礼秘跡省としては問題はないので、しかるべく関係省庁に諮ることで同意しました。
前回や前々回のアドリミナの際には、典礼書の翻訳について今以上に絶大な権限を典礼秘跡省が与えられていたため、ラテン語原文から日本語への翻訳について、日本側の翻訳原案に対して訂正を求めてかなり細か い指摘を、それも厳しく受けたことを思うと、今回の訪問は、お互いの考えを十分に述べる機会として、まだまだこれから当面の間継続する典礼書などの日本語への翻訳作業に関して、明るい見通しを抱かせる面談となりました。
い指摘を、それも厳しく受けたことを思うと、今回の訪問は、お互いの考えを十分に述べる機会として、まだまだこれから当面の間継続する典礼書などの日本語への翻訳作業に関して、明るい見通しを抱かせる面談となりました。
典礼については、日本語への翻訳が常に重要な課題として存在しています。それぞれの地域の教会と、典礼秘跡省がしっかりと連携して作業を迅速に進めるためにも、このように関係者が定期的に出会い意見を交換することは不可欠であることを、改めて確認しました。メールや手紙のやり取りだけでは、物事はなかなか進みません。

朝一番の典礼秘跡省に続いて、福音宣教省へ移動しました。教会的に日本の教会は宣教地ですので、日本の司教たちは、すべて司教省ではなくて福音宣教省の管轄下にあります。アジアで司教省が管轄している司教は、フィリピンの一部を除いた司教たちだけです。
アドリミナの説明をしていて一番難しいのは、聖座を訪問しているのは、教皇からある一定の地域の裁治権を与えられている個々の司教であって、司教団の訪問というのはありません。
ですから、アドリミナの訪問は、司教協議会として同じ日程で一緒に来るように言われていますが、基本的にはそれぞれの司教の訪問であって、司教団のアドリミナではありません。それぞれの司教が任されている宣教または司牧の地域について、自らの責任で報告するのが、アドリミナです。もちろん、個別の課題について話し合うために、司教団が、またはその代表が、聖座を訪問することはありますが、そういった司教団の活動と、アドリミナは異なっています。
それぞれの教区司教(とその補佐)の報告訪問であって、便宜上、日程が一緒になっているものです。100名を超える司教がいる国などでは、いくつものグループに分かれてアドリミナ訪問をしますが、そういったケースでは、司教団の訪問ではないことが明確にわかるかと思います。
さて福音宣教省です。福音宣教省は現在、二か所に事務所を構えています。一か所はスペイン広場の近くに昔からある、いわゆるプロパガンダ・フィデと呼ばれる役所。ここは1622年の創設です。もう一か所は、以前は新福音化推進評議会と呼ばれていた部署。こちらは2010年の創設で、サンピエトロの近くにあります。これが数年前、2022年の省庁再編で一緒になり、現在の長官は教皇様ご自身です。古くからある部署を、初期宣教部門と呼び、責任者はタグレ枢機卿様。新しい部署を世界宣教部門と呼び、フィッジケラ大司教が責任者です。
この日訪問したのは、福音宣教省の初期宣教部門で、こちらは日本における司教の選任から教会活動の様々な点、そして日本の司教たちにとってはバチカンのコンタクト窓口になる部署です。
サンピエトロからスペイン広場まで、一方通行の複雑な経路を、タクシーに分乗して向かいました。
残念ながら、タグレ枢機卿様は、所要のため海外に出かけており、ちょうどこの時間にローマにもどってくるところとのことで、この日はお会いできず、次官のフォルトゥナートゥス・ヌワチュク大司教様が対応してくださいました。(右の写真、中央)。
ナイジェリア出身のヌワチュク大司教様は、教皇大使やジュネーブの国連代表部などに努めた外交官出身ですが、非常に落ち着いた穏やかな笑顔の方で、快く日本の司教たちを迎え、話に耳を傾けてくださいました。
福音宣教省初期宣教部門では、まず日本の司教を代表して、私から主に以下の諸点について、現状報告をさせていただきました。
社会全体の少子高齢化は激しく進み、教会活動にも影響を及ぼし、特に召命の著しい減少の一つの大きな要因になっていること。日本の社会の現実が、いわば神不在の相対的な価値観に支配され、宗教は従来のままの在り方ではその存在意義を失ってしまうこと。
その中で、大規模災害の被災地での長期的な復興支援活動は、愛の業の具体的な実践による福音の証しとして大きな意味を持っ ていること。大阪高松教区が創設されたが、この件を決め進められた福音宣教省の意図が、日本の教会に十分に伝わったとは言い難いこと。福岡と東京の二つの神学院を合併し、東京での一つの神学院としたこと。
ていること。大阪高松教区が創設されたが、この件を決め進められた福音宣教省の意図が、日本の教会に十分に伝わったとは言い難いこと。福岡と東京の二つの神学院を合併し、東京での一つの神学院としたこと。
教会内の様々な新旧の運動体と、それにかかわるもろもろの課題について。
これに対して次官からは、様々な課題について、福音宣教省としては、地域教会の神の民の善益を最優先にして、補完性の原理を守りながら、対話のうちに物事進めていきたいという決意が語られました。さらに、2018年にアジアのための神学院を同省が東京に設立しようと試み、それに伴って内外で混乱を招いたことへの謝罪の言葉がのべられました。
また海外から日本に来られている多くの宣教師の働きに、感謝の言葉がのべられました。また同次官は、各教区からの報告書に目を通すと、日本に滞在する外国籍の方が増えている中で、教会も外国籍信徒の司牧に力を入れている様子がうかがわれ、そのことを高く評価したいと述べ、加えて、イエスご自身も聖家族とともに、エジプトで移民であったし、イスラエルの民もエジプトへ、またバビロンへと移り住んだ移民であったことを考えれば、移民や難民の方々のための司牧活動は、教会にとって重要だと力説されました。
さらに教皇庁宣教事業への献金をはじめ、それぞれの教区がほかの国の教会を支援していることが報告書に記されているが、困難の中にあってもさらに困難を抱える兄弟姉妹に手を差し伸べてくださる日本の教会に、感謝したい。
このあと、それぞれの教区の現状などに基づいて、友好的な雰囲気で情報交換が行われ、昼過ぎには福音宣教省初期宣教部門への訪問は終わりました。
三日目の午前中は、これで終了です。なおタグレ枢機卿様は、金曜日の昼に司教たちの宿舎までおいでくださり、昼食をともにしながら、いろいろと情報交換をする機会を作ってくださいました。
アドリミナの振り返りの第9回目、訪問の週の第三日目、4月10日(水)の午後です。





 未成年者保護委員会の訪問を終え、宿舎に戻り昼食後、午後3時に、大塚司教様、中村大司教様、そして私と、三つの管区を代表して、ローマ市内にある使徒座署名院(最高裁判所)に向かいました。同時間に、前田枢機卿様はアンドレア司教様を伴って、バチカン美術館に向かい、大阪万博への協力を依頼しに行かれました。
未成年者保護委員会の訪問を終え、宿舎に戻り昼食後、午後3時に、大塚司教様、中村大司教様、そして私と、三つの管区を代表して、ローマ市内にある使徒座署名院(最高裁判所)に向かいました。同時間に、前田枢機卿様はアンドレア司教様を伴って、バチカン美術館に向かい、大阪万博への協力を依頼しに行かれました。








(
(編集「カトリック・あい」)
(2024.5.16 カトリック・あい)
日本の司教団は4月8日から13日にかけて、ローマを訪問し、教皇フランシスコとの会見などを行った。その内容について、いまだに司教団としてまとめた具体的な報告書は出ていないが、その中で、大分教区の森山信三・司教が5月1日付けの教区報「こだま」に掲載した報告が、かなり踏み込んだ経緯と感想がのべられているので、大分教区の了解を得て、以下に全文を転載する。
・・・・・・・・・・・





司教団は同日早朝、バチカンの聖ペトロ大聖堂の地下聖堂で、共同司式によるミサをローマ在住の日本人カトリック共同体と共に捧げた後、バチカン宮殿で教皇との出会いが行われた。
教皇は日本の司教たち一人ひとりを温かく歓迎され、およそ1時間にわたって、自由な雰囲気の中でお話しになり、祝福を与えられた。
司教団は8日にローマ到着後、バチカンの福音宣教省、教理省、人間開発省など主な省や、シノドス事務局、「未成年者・弱い立場の成人保護のための委員会」などを訪問、日本のカトリック教会の現状などを報告するとともに、各省、機関から具体的な取り組みなどについて説明を受けた。
13日午前、日本の司教団はローマの城壁外の聖パウロ大聖堂(サン・パウロ・フォーリ・レ・ムーラ)を巡礼し、使徒聖パウロの墓前でミサを捧げ、バチカン定期訪問は、ほぼ終了することになる。
アド・リミナ(ad limina )とよばれるこの定期訪問では、「使徒たちの墓所へ」を意味するその言葉のとおり、初代教会を支え、宣教に尽くし、ローマで殉教した2人の使徒、聖ペトロと聖パウロの墓参りが行われる。
**********
今回のバチカン定期訪問には、日本の全15教区から、以下17名の司教が参加した。※()内は司教叙階年
前田万葉枢機卿・大阪高松大司教区・大司教(2011)/菊地功大司教・東京大司教区(2004)/中村倫明大司教・長崎大司教区(2019)/松浦悟郎司教・名古屋教区(1999) /大塚喜直司教・京都教区(1997)/ 梅村昌弘司教・横浜教区(1999)/ 勝谷太治司教・札幌教区(2013) / 白浜満司教・広島教区(2016) /ウェイン・バーント司教・那覇教区(2018) /ヨゼフ・アベイヤ司教・福岡教区(2018) / マリオ山野内倫昭司教・さいたま教区(2018) /中野裕明司教・鹿児島教区(2018) / 成井大介司教・新潟教区(2020) / エドガル・ガクタン司教・仙台教区(2022) /森山信三司教・大分教区(2022) /酒井俊弘司教・大阪高松大司教区・補佐司教(2018) / アンドレア・レンボ司教・東京大司教区・補佐司教(2023)


 いる姿は、特にバチカンを訪れる観光客の中にあって、目立ちます。移動するのも、宿も食事も全員一緒です。
いる姿は、特にバチカンを訪れる観光客の中にあって、目立ちます。移動するのも、宿も食事も全員一緒です。
 年間に世界中の教区に出した指示を、日本では具体的にどのように生かしているのか、様々に尋ねられたりもします。
年間に世界中の教区に出した指示を、日本では具体的にどのように生かしているのか、様々に尋ねられたりもします。(菊地・日本カトリック司教協議会会長・東京大司教)
(2024.4.8 バチカン放送)
日本の司教団は、教皇庁への定期訪問のためローマを訪れている。
日本のカトリック司教団の「アド・リミナ」(教皇庁定期訪問)が、4月8日(月)より始まった。
アド・リミナ(ad limina )とは、アド・リミナ・アポストロールム(Ad limina apostolorum)の略で、「使徒たち(聖ペトロと聖パウロ)の墓所へ」を意味する。この言葉は本来、ローマにおける使徒たちの墓を訪れるすべての信者たちの巡礼を指していたが、同時に、すべての司教が行うべき定期ローマ訪問を指すようになった。
全世界の司教がそれぞれ順番にバチカンを訪れ、教皇と出会い、地域の教会の状況や問題について報告するこの定期訪問は、基本的に5年に1度行われる。しかし、この間隔は実際には一つの目安であり、必ずしも5年ごとに行われるとは限らない。
ちなみに、今世紀に入ってからこれまでに、日本司教団のバチカンへの定期訪問は、2001年3月(当時の教皇:ヨハネ・パウロ2世)、2007年12月(当時の教皇:ベネディクト16世)、2015年3月(現教皇:フランシスコ)に行われている。
今回の日本の司教団の教皇庁訪問は、新型コロナウイルスによるパンデミックの影響もあり、実に9年ぶりとなった。
14日(日)までのローマ滞在で、司教らは、教皇フランシスコへの謁見と、使徒聖ペトロ、聖パウロのそれぞれの墓前でのミサを中心に、教皇庁の各省や諸機関の訪問等を行う。

ローマ-教皇フランシスコは、スペイン人記者が教皇とのインタビューをまとめた「The Successor」と題する3日発行の本の中で、2005年のベネディクト16世が選ばれた教皇選挙(コンクラーベ)についての質問に答え、自身が彼の選出を阻止する”策略”に利用されそうになったが、それに抵抗し、彼に投票し、4回目の投票で選出されたことを明らかにした。
2005年の教皇選挙は、同年4月2日にヨハネ・パウロ2世教皇がなくなったのを受けて、4月18日から19日にかけて行われた。
この教皇選挙でベネディクト16世が選ばれた経過について「The Successor」の章は、教皇フランシスコ(当時のホルヘ・マリオ・ベルゴリオ枢機卿)が、教皇選挙が終わった夜、食事に出かけたローマのアルゼンチン料理店のオーナーと友人になった経緯から始まる。


(編集「カトリック・あい」)