アーカイブ
・神さまからの贈り物 ⑦「心臓がドキドキしてる!」
カトリックの世界に馴染みのなかった私は「修道女は、物静かでおっとりしている」というステレオタイプな見方を持っていた。でも私が出会ったシスターYさんは、明るくパワフルで、お茶目な一面を見せてくれることもあった。
彼女とは、今から約20年前に、カレン族の村で共に過ごした。心身ともに頑丈で、腕相撲勝負では男子大学生にも負けなかった彼女とは、長年、航空郵便で繋がっていた。
海を越えて届く手紙には、色とりどりの切手が貼ってあり、手書きの文字で住所が書かれていた。彼女は、波乱万丈な毎日を送る私のことを『一番ちっちゃな妹』として、祈り続けてくれていた。
今から数年前、私の心臓がいつもバクバクしていた時期があった。小さな物音にも敏感に怯え、悪夢を見て睡眠がとれなくなった。食も細くなり、外出すると涙が出る始末だった。
「何かがおかしい」と思い、病院で診察してもらったところ、「PTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状が出ていますね」と医師から言われた。自分には関係ない、と思っていた診断に、私はとても混乱した。事情を知ったシスターYが「日本に帰ったら飛んでいくわ!」と約束してくれた。
シスターYが帰省のため日本に来られた翌日、彼女は本当に、私のところに、飛んできてくれた。見慣れた彼女の青色をしたベールがひらりと見えただけで、私は思わず、ほろりとしてしまった。シスターは大きく腕を広げ、満面の笑みでまっすぐ歩み寄り、ぎゅっと私を抱きしめた。
彼女はこう言った。「ああ、よかった!麻衣ちゃんの心臓がドキドキしてる!生きてる!!」。気が付くと、私はシスターYにしがみついて、赤ちゃんみたいに泣いていた。
ひとしきり泣いた後、私の中に今までとは違う考えが浮かんだ-私の心臓は、恐怖でバクバクしているのではなく、「生きたい!」と私に訴えるためにドキドキしていたのだ、と。それは、私が生きていることを心の底から喜んでくれる人が目の前にいたからこそ、気付けたことだった。
今年は2024年、幼い二十歳だった私も、あと少しで四十路に手が届く。中年の入り口にふさわしく、体はふくよかになり、一丁前に白髪も生えてきた。いまの私は、「心臓がバクバクしている」と思っていた頃の過去の私に、こんな言葉をかけてあげたい。
「今の私は、将来の夢を描いてワクワクしているよ。だから、安心して未来に歩いておいで」と。
(東京教区信徒・三品麻衣)
・Sr.阿部のバンコク通信 (85)聖霊の閃きに導かれながら、頑張ろう!
タイの人々は一般に新しい物事に素早く目を付け、関心と興味を持
新製品がいち早く市場に並び、広告宣伝の品が市民の手中に入る早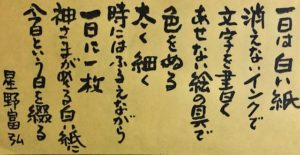 ッション、携帯用品、化粧品、
ッション、携帯用品、化粧品、
自由自在に自己表現した衣食住の数々、キラキラした好奇の目…生
タイ人の気性は、規制束縛されるのを嫌い、自由安泰に都合よく生
他人の目を気にして、ストレスを溜めて生きている日本人が、タイ
私自身をイエスの福音=岩の上に据え、何事にも動ぜずに生きる賢
愛読者の皆さん、お互いに聖霊の閃きを捉え導かれながら、頑張り
(阿部羊子=あべ・ようこ=バンコク在住、聖パウロ女子修道会会員)
・カトリック精神を広める ①聖人の「奇跡」とは…
カトリックでいうところの聖人とは何でしょうか。聖人とは、一言で言えば、「亡くなった後、煉獄を経ずに天国に直行して神の御前に立てる方である」と今、地上で生きている人が証明できる人だろう。
カトリックでは、死後の世界を天国と地獄の他に煉獄があると信仰されている。地獄に行った人は永遠に地獄にあるが、煉獄は、死後すぐに天国に行けない人たちが、生前の罪の贖い(あがない)をするための場所で、幽霊はこの時のものである。手にイエス・キリストと同じ十字架の傷を受けた聖人のピオ神父のもとには、度々、煉獄の霊魂達が訪れ、天国に行けるよう祈って欲しいと訴えたという話が、まことしやかに伝えられている。これこそがまさに幽霊。
ピオ神父は度々、暗闇の中、「そこにいるのは誰だ!」と叫んでいたというが、考えてみたら、こわーい話ではある。
神父のことが書かれている「アレッシオ・パレンテ著、甲斐 睦興 訳、近代文芸社)の逸話を紹介しよう。
時は第二次世界大戦が激しいころ。イタリアのカプチン会の修道院での出来事。或る晩夕食後、修道院の門が閉ざされて長時間経ったとき、階下の入り口の廊下から、「ピオ神父万歳!(ビバ、パードレ、ピオ)」と数人が叫ぶ声が、修道士たちに聞こえた。煉獄の霊魂が、ピオ神父の祈りのお陰で、天国に行くことに決まり、ピオ神父に感謝の意を示すために修道院に来て、叫んだものだった。
そんなこと、知るよしもない修道院長が、部下のジェラルド修道士を呼び出し、「今しがた玄関に入ってきた人たちに、『もう遅いから修道院の外に出なさい』と言うように命じた。修道士は、言われるまま階下に行って、門を見ると、正面の扉は2本の鉄の棒でしっかり閉じられていた。彼はこのことを院長に報告した。翌朝、院長は、ピオ神父に、この出来事の説明を求めた。ピオ神父は説明した。「ピオ神父万歳」と叫んだのは、自分の祈りを感謝しに来た、戦死した兵士たちです、と。
もう一つ紹介したい。これはサレジオ会の創設者、聖ドン・ボスコが若いころ、神学校で仲の良い友人から「なあ、ボスコ、本当に天国ってあるのかい? 約束しようじゃないか。どちらか先に死んだ方が天国に行ったら、生きている方に報告しに来る、というのはどうだろう」と提案を受けた。暫くして、友人は病に伏し、病床でボスコに言った。「前に約束したことを必ず実行する」と。
友人が亡くなった翌晩、20人の神学生たちのベッドが並ぶ寝室に寝ていたボスコは、夜中、多数の馬に引かれた馬車が寝室にやってきた、というくらいの凄まじい音を聞いた。他の神学生たちも同じ音を聞いた。その凄まじい音とともに、亡くなった友人がボスコのベットの脇に立ち、「ボスコ、私は救われた」と大声で叫んで去っていった。
ボスコは、あまりの恐しさに病気になってしまった程で、以来、このような約束を交わすことを金輪際止めたという。20人の神学生が同じ音を聞いているから、この話も信憑性が高い。「完訳ドン・ボスコ」(テレジオ・ボスコ著、サレジオ会訳 ドン・ボスコ社刊)に書かれているが、よく書かれているので一読をお勧めしたい)
亡くなった聖人が、いま天国にいるということを、生きている人がどうやって証明するか。カトリックでは、委員会を作って生前の友人や知り合いに聞き取り調査をする、手紙や著書を読み解くなどして、徹底的に調べる。少しでも疑いがあれば、疑いが晴れるまでは、調査を止める。もし神がその人を聖人の位にあげたければ、神ご自身が人間社会に働
きかけるだろうとカトリックは考える。
調査には、墓をあばくことも入っている。昔は土葬だったため、土の中に葬られている棺を取り出し、中の遺体を調べることまでする。墓をあばく理由は2つある。一つは、もしも墓の中で生き返った場合に(もちろん、めったにはないことだが、実際に生き返った人がいたらしい)、絶望して死んでしまうかもしれない。それでは聖人になれない。
もう一つは、体が腐敗しない、ミイラ化の処置をしていないのに、体が腐らないという奇跡を起こす聖人がいるのである。現在、ミイラ化されているご遺体は、例えば、北朝鮮の初代最高指導者の金日成(キム・イルソン)や、ロシアのレーニン、特殊な防腐処理(エンバーミング)を施され、モスクワ都心の「赤の広場」のレーニン廟に安置されている。これらには、防腐処理が施されている。
読者が信じるか否かは分からないが、肉体が腐らない聖人たちがいる。例えば、南仏のルルドで聖母の出現を体験したことで有名な聖ベルナデッタ。彼女は35歳で亡くなったが、聖母マリアのご出現を体験しただけではなく、修道院内でも聖女の誉れが高く、亡くなってから30年後、聖人の位をあげるのにふさわしいかどうかの調査で、衆人環視の中、墓の中の棺の蓋を開けてみたら、生前と変らない肌に弾力のある聖女が現れ出た。まさにこれは神の恵み。
聖女のご遺体はフランスのヌベール市のサン・ジルダール修道院の聖堂に、安置されており、一般の人も直接、見ることができる。(巡礼ガイドなどは、 ヌヴェール愛徳修道会日本地区のホームページ (neversjapon.org)でご覧になれます)
(横浜教区信徒・森川海守(ホームページhttps://morikawa12.co)
・神さまからの贈り物 ⑥「カレン族の村で愛を浴びる」
二十歳の成人式を迎える日、私はタイ北部のミャンマーの国境近くの山奥にいた。なぜなら、私は生き返りたかったからだ。
そこに住むカレン族の村人たちと『共に生きる』ことを体験するこのプロジェクトは、日本での成人式を諦めてもいい、と思えるほど魅力的だった。人生で初めての挫折を経験し、心身ともに弱り果てていたから、なんとか立ち直りたかった。
「『ご飯だよ』と『ありがとう』さえわかれば大丈夫よ!」と、お世話役のシスターに送り出された。私が滞在した家のモー(カレン語でお母さんの意味)は、向日葵のように明るく、菫のようにはにかんだ笑みを見せる人だった。モーは、惜しみ無く愛情を注いでくれた。
忘れられないのが、とんでもなく辛い料理が出た朝食、あまりの辛さに私が「アヘー(辛い)!」と涙目になった。「オ ティー(水を飲め)」と家族全員が笑った。その時に出された水は、湯冷ましだった。村の水は綺麗だが、慣れていない日本人がお腹を壊すことがあるのを、モーはきちんと覚えていてくれた。翌朝「こっちは辛くないよ」とマイルドな味の料理も作ってくれたのも印象的だ。
モーの愛情によって、日本で凍りついてしまった心がゆっくりと溶けていくのがわかった。一緒に食べ、笑い、祈りを共にすることで、安心が広がる。「モーの愛情を独り占めしていいの?」と聞くと、モーは声を立てて笑い、私をぎゅうっと抱き締めた。
ある日曜のミサで、私は成人のお祝いをしてもらった。白い筒型のワンピースのような民族衣装には刺繍が施され、それは家によって形が違うらしい。そう言えば、前日の昼間にモーが熱心に縫っていたのを思い出した。
祭壇の前で司祭たちから祝福を受けた。心に熱いものがあふれ、緊張感でピンと張りつめていたものが緩んだ。頬には、大粒の涙がぼろぼろ音を立てるようにこぼれた。生まれて初めて体験する深い安堵に「私の心は息を吹き返した」と確信した。
ミサが終わると、村人たちみんなが長蛇の列を作り、順番にブーゲンビリアの花を手渡してくれた。モーの手にも、ショッキングピンクのその花があった。モーは「どうして泣いているの?」というようにニコニコ笑い、両手の指で涙をふいてくれた。私は彼女にしがみつくようにして泣いた。苦しい涙しか流せなかった私が、嬉しい涙を流していた。
そういえば、生きているだけで喜んでもらえた最後の日は、いつだっただろうか?と振り返った。 物心ついた時には、既に周りの期待を背負って生きていたような気がする。
日本社会では効率のよさが重視され、私は生きづらさを感じることが多い。けれども、今日も神さまは「あなたを愛している」ということを周囲の人たちを通して、伝えておられるのがわかる。
過去の私は、苦しいことは避けたいと思っていた。でも、苦しい時の私は必ず誰かからの優しさを受け取っていた。必ず試練とともに逃げ道がある。そのことは、私に大きな希望をもたらした。
新しい一年が、みなさまにとってすばらしいものとなりますように。
(東京教区信徒・三品麻衣)
・愛ある船旅への幻想曲 (35)新年、教会がどう動いて行くか、しっかりと目を覚ましていよう
イエスの御降誕、
2023年12月24日、教皇フランシスコは、「
“人間性”・・
私は、戦争を経験していない。以前、アメリカ人の若者から「
今年もイエス・
イエスのご降誕を祝う荘厳な司祭の祈りと、それに応え、心からミサ曲
「淫行、汚れ… 敵意、争い…利己心、分裂… このようなことを行う者は、神の国を受け継ぐことはありません。これに対し、霊の結ぶ実は、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、
一つ一つの小さな教会の熱心な祈りが世の平和のためにどれだけ必
降誕祭ミサに限らず、
2024年、世界がそしてカトリック教会がどう動いていくのか。
(西の憂うるパヴァーヌ)
(故森司教コラム再掲)②20数年前、日本の司教団は福音宣教活性化のため、すべての信者に大胆な呼びかけをしたが…
今から20数年前のことであるが、日本の司教団が、日本社会での福音宣教の活性化のために、日本の教会のすべての信者に向けて、大胆な呼びかけをしたことがある。その中に次のような一文があった。
「信仰を,『掟や教義』を中心とした捉え方から,『生きること、しかも,ともに喜びをもって生きること』を中心とした捉え方に転換したいと思います。」
「『掟や教義』から『生きること』を中心にした信仰の捉え方への転換」。この呼びかけは、伝統的な信仰生活に慣れ親しんできた西欧の人々には,奇異な印象を与えるかもしれない。が、その背後には,教会の扉を叩く人々の中に、心の傷ついた人や精神的に病む人々が多くなっていたという特殊な事情があった。
周知のように、能力主義の浸透で競争が激化した結果、日本社会は経済的には発展したが、その陰で家族はその力を弱め、人と人とつながりはバラバラになり、いざ人生の壁に直面し、思い悩なければならなくなったとき、身近なところに、親身になって相談にのってくれる人を見出すことは,難しくなっていた。その表れが、自殺者や孤独死の増加であった。
政府は、学校や職場にカウンセラーなどの専門家を置くようにしたり,ケースワーカーの増員を図ったりして対応しようとしてきたが、人の悩みや苦しみは複雑であり、カウンセラーやケースワーカーとの相談には限界がある。苦しみ悩む人々が、相談相手として最後に思いつくのが、教会であったのである。教会に行けば,生きていく力を見出せるのではないかという期待感を抱いて、教会の門を叩いていたのである。
ところが、「教え」を伝えることに軸足をおいてきた教会は、こうした人々を求道者として受け入れ,教会の教えや聖書のクラスを紹介し、やがては洗礼に導いていくという流れの中で対応してきていたのである。 しかし、それは、必ずしもふさわしい対応ではなかった。と言うのは、教えは、日本人には馴染みのない用語がふんだんに使われていて、心の病んでいる人々や心身が疲れ果てている人々には,難しい。その上、そういう人々に限って、周りの人とコムニケーションをとることが難しく、たとえ教えのグループに入っても、人間関係に耐えられなくなって、いつの間にか姿を消してしまうのである。
悩み苦しむ人々が、折角教会の扉を叩きながら,教会に馴染めず、いつの間にか姿を消してしまうということは,残念なことである。「教えに軸足を置いた宣教姿勢」に限界があることを知った司教たちは,その転換を図ろうとしたのである。
「生きることを中心に」とは、厳しい人生を生きる孤独な人間のありのままを包み込むことに軸足を置いて、人と向き合うことである。人々は、苛酷な人生の現実にぶつかって、存在「being」そのものが弱り果て、いたたまれなくなって、教会の扉を叩こうとしているのである。そんな人々に何よりも先に必要なことは、揺らぐ存在「being」そのものをあたたかく包み込んでいくことである。「教え」は,その後のことである。
日本の司教たちのこの呼びかけは、日本の教会全体に「労苦するもの,重荷を負うものは,私のもとに来なさい。休ませよう」という柔和謙遜なキリストの生きた証人になることを呼びかけた、と言えるのである。
(2016.10.1記)
“シノドスの道”に思う ⑦新年にあたって、日本の民話やグリム童話からシノドスを考える
*「猿長者」
日本の民話を、あらすじです。まず、鹿児島県大島郡に伝わる「猿長者」。
東長者は金持ちで、西長者は爺さんと婆さんの二人暮らしで子供も金もない貧乏者であった。ある師走の年の瀬に、神様は貧しい飯もらい坊主の姿になって、まず東長者の家へ行って、「すまないが、行きどころがないので、どうか宿を貸してください」と申された。ところが東長者は「今は年の瀬だぞ、帰れ」。
飯もらい坊主は、こんどは西の爺さん夫婦の家へやって来て「宿をかして下され」。夫婦は「さあさあ、早く入りなされ。食べる物は何もありませんが、粟種を入れたお湯でもおあがりなされ」と坊主を喜んで迎えます。三人が食べ始めた時、坊主は二人に「一升鍋に青葉を三枚入れて、水を入れて炊いてごらんなさい」と言う。婆さんは言われた通りにすると、一杯の肴が出てきた。さらに坊主は財布から米粒を三つ取り出して、「さあ、これを釜に入れてご飯を炊きなさい」。すると釜一杯のご飯ができた。さらに坊主は「爺さん婆さん、お前たちは貧しくて年をとっているが、宝がほしいかい、それとも元のような若さがほしいかい」と聞く。「若さがほしいです」と答えると、二人は若夫婦になった。
次の日、そのことを聞いた東長者は「とんでもないことをしてしまった。うちに泊めていたら、あのような運をさずかったものを。今からこの家に来てもらおう」と。そうして呼ばれた坊主は、東長者に赤い薬を渡した。それを風呂に入れて、夫婦で湯をあびると、二匹の猿になってしまった、という。
*「大年の客」
次に、岩手県の「大年の客」。
大晦日の晩、ある貧しい家に、どこからか一人の座頭(目の見えない人)が来て、泊めてくれと頼んだ。主人は困って、「うちは貧乏だから、どうか隣の家の長者さまの家に行って泊まってください」と答えたが、座頭は「俺は貧しい家で結構だ」と言って、その家に泊まった。
明くる朝、座頭は「若水をくむ」と言って井戸ばたに行くが、すべって井戸にはまってしまった。家の人たちが縄を下ろしてやると、座頭は「これこれ家の人たち、大きな声で『身上』『身上』と掛け声をかけて縄を引き上げなされ」と言う。その通りにして、座頭は井戸の外まではい上がり、出しなに「上がった、上がった」と大きな声を上げた。それからというもの、この家はだんだんと豊かになって行った。
それを知った隣の長者は、不思議に思って、彼らから、わけを聞き出した。そして、ある年の大晦日に座頭を見つけ出し、嫌がるのを無理やり自分の家に泊め、同じようにして、もっと金持ちになろうとしたが、貧しくなってしまった…。
*「貧乏人と金持ち」
三つ目はドイツのグリム童話の「貧乏人と金持ち」です。
昔々、まだ神様が自身で地上を歩きまわっていた頃、ある晩、神様は自分の宿に着く前に日が暮れてしまった。道のそばに、二軒の家が向き合って立っていた。一方は大きくて立派な金持ちの男の家。もう一方は小さくみすぼらしい貧乏な男の家。
神様は「金持ちなら負担になることもあるまい。今夜はあの家で泊まるとしよう」。神様がこつこつと戸をたたくと、金持ちの男は窓を開け、「なんの用か」とたずねる。「どうか、一晩だけ宿をおかしください」と答えると、粗末ななりをしているを見て、「だめだね、うちの部屋は薬草などでいっぱいだ。よそへ行ってくれ」と断った。
神様は今度は向かい側の貧乏な男の家に行く。戸をたたくと、貧乏の男が戸を開け、「お入りください」と歓迎し、貧しいながらも精いっぱいのもてなしをした。翌朝、外に出た神様は「お前さ
んたちは情け深く、信心深いから、三つの望みをかなえてあげよう」と言い、古くてみすぼらしい家が、新しい大きない家になった。
そのことを知った隣の金持ちは、急いで馬を走らせ、去って行こうとする神様を引き留め、自分のところにも泊まりに来るように、そして望みをかなえてくれるように、と執拗に願う。神様が承知してくれたので、喜んで家に戻ったが… 貧しくなってしまった。
*三つの共通点
この3つの話は国は違いますが、内容はほぼ同じ、貧しい人と金持ちの話。貧しい人は、旅人への同情や憐れみから、自分の家に迎え、もてなす。喜んだ旅人は大きな報いを与える。それを見た金持ちは、「困った人を助けよう」という気持ちからではなく、「もっと豊かになりたい」という欲望から旅人を無理やり泊めようとする。貧しい人がしたことと、形だけは同じことをするが、惨めな結果になる-というパターンです。また、泊まる所が無くて困っている貧しい旅人が、実は神様だったという点も同じです。
*個々の文化を超えている神、人類普遍の民衆の神
ではどういう神でしょうか。2つの日本の民話に出てくる神は、べつに神道教学に基づく神ではないし、グリム童話の神も、一応はキリスト教の神ですが、
この童話の元となった民話を語り継いだ民衆がキリスト教の教義や神学を知っていたわけではないでしょう。ラテン語を読めず、聖書を読む機会もなかったのですから。登場人物の貧しい人も、教義や神学をもとにした行動をとったわけではありません。ここに出てくる「神」は「世界の民衆に共通する憐れみの神」とでも言いましょうか。
日本でもドイツでも同じ話、同じ行動パターンに同じ結果があるということは、この世界を治めている「神」が、つきつめていけば、同じ存在だ、ということではないでしょうか。キリスト教の神、神道の神という区別は、文化的に頭の中で立てられたもの。『現代世界憲章』でも述べられているように人間は誰でも「神の像」に造られていますし、人間の中には「神からの種」「永遠性の種」があります。世界中で「苦しい時の神頼み」をしたことのない人はほぼいないのではないでしょうか。その時、どの神に祈るかと、いちいち考える人はいないでしょう。
*黄金律はシノダリティに通じる
日本の民話でもドイツのでも貧しいほうは旅人を受け入れ、もてなした。「共に歩む、共に生きる」というシノダリティを無意識に実践しています。そして
その旅人が神であったというのは、マタイの福音書第25章「私の兄弟であるこの小さい者にしたのは、私にしてくれたことなのである」という言葉に合致し
ます。旅人が神とは知らずに、可哀想な人だと思って泊めました。実生活において、神への信仰は隣人愛(憐れみ)と分離できないのだと思います。イエスの言う「人にしてほしいと思うことを、あなたも人にしなさい。(これこそ律法と預言者である)」(マタイ7:12)という黄金律はユダヤだけでなく、どの文化にも共通するものです。なので、「聖書と伝統」だけでは足りず、人類に普遍的な、多文化共生的な視点でキリスト教を理解し、また教会を運営すること
が求められます。
*共通祭司職を中心にした教会へ
現代まで教会が存続してきたのは、教義的なことを知らなくても、信仰を生きた民衆、大多数の一般信徒がいたからです。「信仰の感覚」を持つ信徒一人一人を重視し、神の民の声を聴くこと、また、これまでのように「教える人」と「教えられる人・学ぶ人」を厳密に分けないことは、当然のことです。したが
って教会の構造や運営も、共通祭司職を基本において再構築するべきではないでしょうか。
このように、これまでのヒエラルキー的教会の叙階に基づく「役務的祭司職」よりも、全信徒が持つ「共通祭司職」をもっと重視し掘り下げること、もっと信徒が活動できるようにすることが「シノダリティのためのシノドス」には求められていると思います。2023年10月のシノドス総会第一会期は参加者たちにとっては“シノダルな集会”だったのでしょうが、教区、国、大陸別の歩みを十分踏まえた「シノダリティのためのシノドス」と言えるのかどうか。
例えば、第一会期の文書には「共通祭司職」という言葉は一つもないばかりか、それを警戒するような部分さえあります。今年10月の第二会期に至るこれからの歩みが、どのようになされるのか、注視して行きたいと思います。
*文中の日本の民話は『日本の昔ばなし』岩波文庫全3巻に所収。
(西方の一司祭)
・Chris Kyogetuの宗教と文学⑨「ナボコフの『賜物』とマタイによる福音書25章」
「つまり、引いていく潮のように、蝶たちは冬を越すため、南に向かうんだ。でも、もちろん、暖かいところに辿り着く前に、死んでしまう」(ウラジミール・ナボコフ「賜物」より)
「賜物」というものを考えると、「持って生まれた才能」ということも意味するので、自分の人生を振り返る人は少なくはないと思う。「一体自分に、何が与えられていたのか」-それを敢えて前置きにしてしまうが、イエス降誕前より、個人の才能はギリシャ語で(Theodor)と神からの贈り物と考えられていた。ロシアという国の言語の歴史を辿ると元々は抽象的であり、聖書の「神は言葉と共にあった」を再現したように、聖書伝来と共にアルファベットが出来た国だと聞いた。ナボコフ自身、ロシア革命後に亡命し、「賜物」は彼にとって最後のロシア語で書かれた長編小説となった。
この作品は、ナボコフの自伝ではないかと言われるが、本人は否定している。しかし、それだけこの小説はナボコフの人生、例えば亡命に限らず、蝶の専門家であったり、チェスプロブレムに費やしていたりと、類似点が多いようだ。
主人公ヒョードルは作家への才能を「賜物」と信じている。母親も息子の才能を理解していて、行方知れずになった昆虫学者の「父」についての小説を書くように促されるが、彼は父を尊敬していたからこそ、父の伝記が世間の好奇な関心に晒されることを拒んだ。それで、彼は別の人物の伝記を書くことにした。リアリズムと夢想、幻想的な思索を行ったり来たりの作品だが、そこには昆虫学者の父親を追いかける思索の旅ともなる。
作中で母国を失うということ、愛着を持たない住まいに対しての喪失感を「読者よ」と語りかけ、それはどんなことかをストレートに表現している。それが私には印象深い。
「涙を流したり、感傷深くなるわけでもなく、魂の最良の一隅に置いて、命を吹き込んでやれなかっただけではなく、殆ど気にとめることもないまま、いま永遠に見捨てていく物たちへの憐みを感ずるのだ」彼の、無理して想像で愛そうとしない心や、悲劇を想像で補おうとしないその心が、うまく詩情へと変換され、より読者の想像力を掻き立てている。
賜物については、マタイによる福音書25章の「タラトンのたとえ話」に書かれているが、よく説明されるのは「神が与えた才能」ということだ。才能の数は多いか、少ないのか、たとえ通貨一枚でも「価値」のあるものとしている。しかし、実際には聖職者でさえも、この話の続きをあまり触れることがないまま、「贈り物」と同義語のように単純に説明をしてしまうことが多い。
まず、これは神からもらった「タラントン」、ではなくそもそも、『預かった』タラントン(財産)ということをまず覚えておかなければならない。増やせた人間は神から褒められたが、一枚しかもらってない人間が土に埋めたら、神は怒った。そして神は言われた。「誰でも持っている人はさらに耐えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられる。この役に立たない僕(しもべ)を外の暗闇に追い出せ。そこで泣き喚いて歯ぎしりするだろう」。
この箇所は、非情と思われることが多く、「キリスト教」の神を嫌われる箇所でもあるみたいだが、この部分だけを見れば、仏教の「無常」ともよく似ている。尊師(釈迦)が死の床に入る前に、弟子たちに、「諸々の事象は過ぎ去るものである。怠ることなく修行を完成なさい」と、修行を続けることを言った。それから、侍者であるアーナンダに、「虚空のうちに在って地のことを想うている神々がいる」と語っている。
イエスの「たとえ話」は壮大な神の知恵や教え、預言をまとめただけでなく、イエスの話を通すことで、父と子と聖霊を循環させると私は考えている。だからこそ、一度わからなくても、よく耳を済ませて、心を開いておく必要がある。タラントンは、神から「頂いた」ものではなく、いずれは返すものであるので増やさなければならないものだと。
「タラントン」というのは、主人から預かっておきながら、直ぐに機転を効かせて増やした人もいれば、臆病になってしまって土に埋めたものがいるように、それが何なのか、本来は分かりにくいものなのかもしれない。特に、ナボコフの「賜物」のように目指すものが作家や詩人という「芸術家」については、最も例えやすいが、他者にとって難解な才能なのかもしれない。この話が簡単に説明できないように、祖国を失う運命ですらもそれは「ギフト」だったのか? それは終盤である五章の亡命後で、出版と愛がテーマとなっても隠喩めいている。
亡命の感情というものは定点を持たない。私の祖父も、ロシア革命の亡命者だったそうだ。当然ながら、棄教もしている。葬儀は葬儀屋で仏教葬になった。生前、認知症になる前はルター版の聖書が気に入っていたので「プロテスタントでもいいかな」とは言っていたそうだ。そういう話と私の「信仰」は全く別の歯車として動いていた上に、「亡命者」というのは祖父の死後に聞かされた話だった。象牙の聖典(聖書だったかどうか不明)や、イコン画などは引き取り手があるとか、お金になるとかで、親戚同士で分けあった。それなのに我が家には回ってこなかった、と、その話は覚えている。特に欲しかったのは象牙のものだったが、私に見せたかった、と父親が話した。
祖父は、意識がまだしっかりしている時にこうも言ったそうだ。「私達は、キリストの苦しみを背負うことを享受していた。けれども、それを利用される、もう懲り懲りだ」。
その無常に対してどう思ったのか、想像し難いものだったので、言葉になったことはない。だからこそ作中の「涙を流したり、感傷深くなるわけでもなく、魂の最良の一隅に置いて、命を吹き込んでやれなかっただけではなく、殆ど気にとめることもないまま、いま永遠に見捨てていく物たちへの憐みを感ずるのだ」という箇所が特に、印象に残った。
カトリックに入ると、そういった悲壮と無縁のように思えた。けれども、実態は「キリストの苦しみを背負うことに対して、利用される」その言葉が突き刺さるようなこともあった。私が「過去」に尊敬していた神父は、神はどんな罪も許してくれて、愛してくれると神の審判の代弁者のようだった。
けれども、その人も不正があった上に、聖職者として失格な人だった。(教会法上)けれども、その人が言っていた「神の愛」だけは揺るがないものとして私に残り続けている。「ゴミ」のような存在だと思った日もあったが、私は破片を拾うことにする。それが、私の「経験」であるからだ。私は安易に、そう言った経験に「感謝」はしないし、苦しみを「ギフト」とは言わない。簡単に、神が与えた「試練」だとも言わない。そんなものは簡単に言ってはならない。だからこそ違うアプローチで語り直そうと思う。
神から預かったもの、それは何なのか不確かで、直ぐに気持ちを幸せにしてくれるものだけではないのかもしれない。けれどもキリスト者は常に、「無常」のように思える現実でも、神から預かっているという意識を持ち続けなければならない。世に放り出された感覚であっても、イエスの譬え話は私達と神を繋ぐ通り道である。最後に、ロシア語で「賜物」Дар(ダール)は逆から読むと、paД(ラート)「嬉しい」と意味する。彼はこの書籍のタイトルを元々は、Да(ダー・Yes)としていたそうだ。それすらも、逆から読めばaД(アート・地獄)と、表裏一体が付き纏っている。
神は与えることもあれば、奪うこともある。全て、人の叡智で語れないながらでも、私達は支え合って言葉を交わす。言葉にならないことでも、言葉にして。足りない言葉に添えるために、愛や涙がある。たとえば、自分の不幸や、大切な人の不幸に、そして、私ながらに… 私ながらに。私の言葉で、多くの不幸に閃きを与えることはできないが、本当に自分を奪えるのは「神」だけだと、そう思うことにしている。だから、まだ「残っている」。それは聖職者であっても、何人(なんびと)も完全には奪えない。世は魂の尊厳や全てを奪えないし、奪わせてはならない。
臆病になってはならない、土に埋めてはならない。常に増やすことを意識すること。
引用の詩のように辿り着けなかった蝶は、母国に帰れなかった。けれども、天の国へ、「それ」は返せたのかもしれない。天との繋がりが羽ばたきとなること、生命力。 それが強さになるのではないのではないだろうか。
(Chris Kyogetu)
・Sr.阿部のバンコク通信(84) 漫画で体験するイエスの福音のタイ語版の出版、クリスマスに間に合いました!
クリスマスを前に、“ซุปเปอร์ฮีโร่ของฉัน” My Super Heroと題する漫画で体験するイエスの福音を、タイ語-
サンパウロ出版、柴田千佳子作画「はるかなる風を超えて」1.
日本の漫画が好きなタイの人々に、まさに「福音」です。
少しでも安く頒布するために、校正中の試し刷り抱えて予約の注文取りに回りました。学校、教会、友人…
で交渉しました。そのかいあってか、4000冊余りの注文がとれ、姉妹の了解を得て7000冊印刷しました。
本が出来上がりると、30年来の付き合いの印
漫画は、巷のクリスマスセールから始まります。
愛読者の皆さん、主のご降誕、おめでとうございます。
漫画物語は現実の世界に戻り、
”Gloria in excels Deo et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.” 心よりの信仰告白を捧げ、世界中の人々を胸に祈ります。そして… Happy Birthday Jesus in your heart!
(阿部羊子=あべ・ようこ=バンコク在住、聖パウロ女子修道会会員)
・「大きな光輝く星は… クリスマスに思うこと」(西方のある司祭)
三人の博士が見た星は、どんな星だったのだろう。
普通にはあるはずもないところに、大きな光り輝く星が、周りの星々を圧倒するような様子で輝いていたのだろう。それが「ユダヤ人の星」「メシアの星」である、と博士の心に、静かに、しかし力強く語りかける声を一人ではなく、同時に三人の博士が聴いたのだろう。
「これは間違いない」と確信した三人は「この星の示す人が、自分たちの運命にも関わる大事な存在なのだ」となぜか知らないが、分かったので、誰ともなく、「さあ、出かけよう、拝みに行こう」と言い出した。砂漠の旅は楽ではなかったが、希望のほうが心を占めていたので、歩み続けることができた。
エルサレムに着いて間もなく王宮でヘロデ王に会ったが、彼はそのことを理解していないし、星が示す場所はここではない、と知って、その場を後にした。外に出ると、夜でもないのに東方で見た星が輝き、「ついて来なさい」と言うかのように、彼らの先を進んでいく… 不安は消えて、喜びが三人に湧いてきた。
そして間もなく、一軒の家を見つけ、中に入ってみると、幼子は母とともにいた。彼らはひれ伏して拝み、用意してきた宝の箱を贈り物として捧げた。そして幼子と母のやさしい眼差しを心におさめ、
長居はせず、別れの言葉を述べて 別の道を通って、帰っていった。それぞれの心に幼子の姿を思い出しながら…。
☆
皆さま、主イエスの誕生おめでとうございます。一人ひとりの心に幼子イエスがとどまってくださいますように。
“真砂(まさご)なす数なき星の其(そ)の中に吾(われ)に向かひて光る星あり“
正岡子規の短歌ですが、この星は、皆さん一人ひとりを導く星でもあります。
(西方のある司祭)
・【森司教のことば/再掲】「極貧、独裁者、難民、虐殺、民族宗教などキーワードで キリスト誕生の物語を読み解く」
クリスマスが近づくと、日本社会全体がクリスマス一色に染まってしまう。デパートや商店街には、イルミネーションが飾られ、街中にはジングルベルの軽やかな歌が流れ、人々は明るい気分に包み込まれる。
しかし、それは、福音書が伝えるキリストの誕生の物語に込められている光とも異質のものであり、キリストがこの世界にもたらそうとしたメッセージとも無縁のものである。それは、キリストの誕生の場面を伝えるルカ福音書、マタイ福音書を丁寧に読んでみれば、明らかである。
*極貧
ルカ福音書が伝えるキリストの誕生の物語には、天使たちや羊飼いたちが登場し、表面的には、心を和ませるような牧歌的な印象が与える。が、それに惑わされてはならない。というのは、天使たちや羊飼いたちが登場する前に、ルカ福音書は、「キリストが極貧の中に生まれた」ことを殊更に強調しているからである。
注目すべきは、「宿屋には彼らが泊まる部屋がなかったからである」と記している点である。
『泊まる部屋がなかった』理由として、客が多くて、どの宿も満室だったということも、考えられなくもないが、それよりも、私には、ヨゼフに泊まるためのお金がなかったから、とか、ヨゼフが人々の目にみすぼらしく映ったから、と思われるのである。もし、金銭的に余裕があれば、そして裕福そうにみられれば、部屋の一つや二つは融通してもらえたかもしれない。
貧しい者が、店先や宿屋の入り口で軽んじられたり、拒まれたりしてしまうのは、今も昔も同じである。またそこから、人々の冷たさも伝わってくる。臨月を迎え、お腹が大きくなった女性を目のあたりにしても、誰も、便宜を図ろうとしなかったのである。部屋がなかったとしても、片隅にでも、休ませることぐらいは出来たはずである。
貧しさ。そして人々の冷たさ。そこで、止むを得ず、マリアは、家畜小屋で、出産することになる。家畜小屋とは、羊飼いたちが風雨を避けるための避難所のようなものである。決して心地よい小屋ではない。キリストは、柔らかなベットではなく、飼い葉桶に寝かせられる。
誰もが、貧しさには目を背け、貧しさから抜け出そうと、必死である。貧者には哀れみの目を向けることがあっても、貧者に助けを求め、貧者に頼ろうとする者は、一人もいない。
貧しさの極みの中で生まれた赤子が、人類の希望となるとは、常識的は理解できないことである。その非常識に目を向けるように呼びかけたのが、天使たちなのである。
羊飼いたちは、天使たちの呼びかけを受けて、キリストの誕生の場に駆けつけていく。彼らが、何を感じとったか、記されていない。しかし、何かを感じとったに違ない。
天使たちの呼びかけは、私たちへの呼びかけでもある。飼い葉桶に横たわるキリストには、人々を引き寄せる権力も富もなく、きらびやかなイルミネーションもない。しかし、そこに全人類を支え照らす光と力が満ちあふれているのである。
極貧の中に誕生したキリストに出会うためには、私たちも裸になる必要がある。自らの心の奥に入り、自らを裸にし、自ら貧しい存在であるということを見極めることである。実に、キリストは、貧しさの中に誕生しているからである。私たちに求められるのは、私たちが普段囚われてしまっている常識的な価値観の転換である。


