*「猿長者」
日本の民話を、あらすじです。まず、鹿児島県大島郡に伝わる「猿長者」。
東長者は金持ちで、西長者は爺さんと婆さんの二人暮らしで子供も金もない貧乏者であった。ある師走の年の瀬に、神様は貧しい飯もらい坊主の姿になって、まず東長者の家へ行って、「すまないが、行きどころがないので、どうか宿を貸してください」と申された。ところが東長者は「今は年の瀬だぞ、帰れ」。
飯もらい坊主は、こんどは西の爺さん夫婦の家へやって来て「宿をかして下され」。夫婦は「さあさあ、早く入りなされ。食べる物は何もありませんが、粟種を入れたお湯でもおあがりなされ」と坊主を喜んで迎えます。三人が食べ始めた時、坊主は二人に「一升鍋に青葉を三枚入れて、水を入れて炊いてごらんなさい」と言う。婆さんは言われた通りにすると、一杯の肴が出てきた。さらに坊主は財布から米粒を三つ取り出して、「さあ、これを釜に入れてご飯を炊きなさい」。すると釜一杯のご飯ができた。さらに坊主は「爺さん婆さん、お前たちは貧しくて年をとっているが、宝がほしいかい、それとも元のような若さがほしいかい」と聞く。「若さがほしいです」と答えると、二人は若夫婦になった。
次の日、そのことを聞いた東長者は「とんでもないことをしてしまった。うちに泊めていたら、あのような運をさずかったものを。今からこの家に来てもらおう」と。そうして呼ばれた坊主は、東長者に赤い薬を渡した。それを風呂に入れて、夫婦で湯をあびると、二匹の猿になってしまった、という。
*「大年の客」
次に、岩手県の「大年の客」。
大晦日の晩、ある貧しい家に、どこからか一人の座頭(目の見えない人)が来て、泊めてくれと頼んだ。主人は困って、「うちは貧乏だから、どうか隣の家の長者さまの家に行って泊まってください」と答えたが、座頭は「俺は貧しい家で結構だ」と言って、その家に泊まった。
明くる朝、座頭は「若水をくむ」と言って井戸ばたに行くが、すべって井戸にはまってしまった。家の人たちが縄を下ろしてやると、座頭は「これこれ家の人たち、大きな声で『身上』『身上』と掛け声をかけて縄を引き上げなされ」と言う。その通りにして、座頭は井戸の外まではい上がり、出しなに「上がった、上がった」と大きな声を上げた。それからというもの、この家はだんだんと豊かになって行った。
それを知った隣の長者は、不思議に思って、彼らから、わけを聞き出した。そして、ある年の大晦日に座頭を見つけ出し、嫌がるのを無理やり自分の家に泊め、同じようにして、もっと金持ちになろうとしたが、貧しくなってしまった…。
*「貧乏人と金持ち」
三つ目はドイツのグリム童話の「貧乏人と金持ち」です。
昔々、まだ神様が自身で地上を歩きまわっていた頃、ある晩、神様は自分の宿に着く前に日が暮れてしまった。道のそばに、二軒の家が向き合って立っていた。一方は大きくて立派な金持ちの男の家。もう一方は小さくみすぼらしい貧乏な男の家。
神様は「金持ちなら負担になることもあるまい。今夜はあの家で泊まるとしよう」。神様がこつこつと戸をたたくと、金持ちの男は窓を開け、「なんの用か」とたずねる。「どうか、一晩だけ宿をおかしください」と答えると、粗末ななりをしているを見て、「だめだね、うちの部屋は薬草などでいっぱいだ。よそへ行ってくれ」と断った。
神様は今度は向かい側の貧乏な男の家に行く。戸をたたくと、貧乏の男が戸を開け、「お入りください」と歓迎し、貧しいながらも精いっぱいのもてなしをした。翌朝、外に出た神様は「お前さ
んたちは情け深く、信心深いから、三つの望みをかなえてあげよう」と言い、古くてみすぼらしい家が、新しい大きない家になった。
そのことを知った隣の金持ちは、急いで馬を走らせ、去って行こうとする神様を引き留め、自分のところにも泊まりに来るように、そして望みをかなえてくれるように、と執拗に願う。神様が承知してくれたので、喜んで家に戻ったが… 貧しくなってしまった。
*三つの共通点
この3つの話は国は違いますが、内容はほぼ同じ、貧しい人と金持ちの話。貧しい人は、旅人への同情や憐れみから、自分の家に迎え、もてなす。喜んだ旅人は大きな報いを与える。それを見た金持ちは、「困った人を助けよう」という気持ちからではなく、「もっと豊かになりたい」という欲望から旅人を無理やり泊めようとする。貧しい人がしたことと、形だけは同じことをするが、惨めな結果になる-というパターンです。また、泊まる所が無くて困っている貧しい旅人が、実は神様だったという点も同じです。
*個々の文化を超えている神、人類普遍の民衆の神
ではどういう神でしょうか。2つの日本の民話に出てくる神は、べつに神道教学に基づく神ではないし、グリム童話の神も、一応はキリスト教の神ですが、
この童話の元となった民話を語り継いだ民衆がキリスト教の教義や神学を知っていたわけではないでしょう。ラテン語を読めず、聖書を読む機会もなかったのですから。登場人物の貧しい人も、教義や神学をもとにした行動をとったわけではありません。ここに出てくる「神」は「世界の民衆に共通する憐れみの神」とでも言いましょうか。
日本でもドイツでも同じ話、同じ行動パターンに同じ結果があるということは、この世界を治めている「神」が、つきつめていけば、同じ存在だ、ということではないでしょうか。キリスト教の神、神道の神という区別は、文化的に頭の中で立てられたもの。『現代世界憲章』でも述べられているように人間は誰でも「神の像」に造られていますし、人間の中には「神からの種」「永遠性の種」があります。世界中で「苦しい時の神頼み」をしたことのない人はほぼいないのではないでしょうか。その時、どの神に祈るかと、いちいち考える人はいないでしょう。
*黄金律はシノダリティに通じる
日本の民話でもドイツのでも貧しいほうは旅人を受け入れ、もてなした。「共に歩む、共に生きる」というシノダリティを無意識に実践しています。そして
その旅人が神であったというのは、マタイの福音書第25章「私の兄弟であるこの小さい者にしたのは、私にしてくれたことなのである」という言葉に合致し
ます。旅人が神とは知らずに、可哀想な人だと思って泊めました。実生活において、神への信仰は隣人愛(憐れみ)と分離できないのだと思います。イエスの言う「人にしてほしいと思うことを、あなたも人にしなさい。(これこそ律法と預言者である)」(マタイ7:12)という黄金律はユダヤだけでなく、どの文化にも共通するものです。なので、「聖書と伝統」だけでは足りず、人類に普遍的な、多文化共生的な視点でキリスト教を理解し、また教会を運営すること
が求められます。
*共通祭司職を中心にした教会へ
現代まで教会が存続してきたのは、教義的なことを知らなくても、信仰を生きた民衆、大多数の一般信徒がいたからです。「信仰の感覚」を持つ信徒一人一人を重視し、神の民の声を聴くこと、また、これまでのように「教える人」と「教えられる人・学ぶ人」を厳密に分けないことは、当然のことです。したが
って教会の構造や運営も、共通祭司職を基本において再構築するべきではないでしょうか。
このように、これまでのヒエラルキー的教会の叙階に基づく「役務的祭司職」よりも、全信徒が持つ「共通祭司職」をもっと重視し掘り下げること、もっと信徒が活動できるようにすることが「シノダリティのためのシノドス」には求められていると思います。2023年10月のシノドス総会第一会期は参加者たちにとっては“シノダルな集会”だったのでしょうが、教区、国、大陸別の歩みを十分踏まえた「シノダリティのためのシノドス」と言えるのかどうか。
例えば、第一会期の文書には「共通祭司職」という言葉は一つもないばかりか、それを警戒するような部分さえあります。今年10月の第二会期に至るこれからの歩みが、どのようになされるのか、注視して行きたいと思います。
*文中の日本の民話は『日本の昔ばなし』岩波文庫全3巻に所収。
(西方の一司祭)
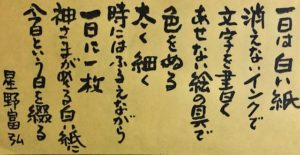 ッション、携帯用品、化粧品、
ッション、携帯用品、化粧品、


